セメンザ教授は、低酸素状態で腎臓がエリスロポエチンを分泌して赤血球を増やし,酸素の運搬能力を上げようとする際に、この反応を活性化するタンパク質を発見。
これをHIF-1(低酸素誘導因子,hypoxia-inducible factor 1)と名付けたのが最初で、後に遺伝子同定されています。
この低酸素反応の研究が評価され、後に、酸素が十分な状態では逆にHIF-1αを減らす仕組みを研究した2人の研究者との共同受賞となったようです。
実は、昨年末に知り合いの家でテレビを見ていると、サイエンスzeroという日本の番組で、偶然この特集をしていました。
麻酔科領域など、低酸素に絡む分野の研究では有名な遺伝子で、虚血の研究をしていた妻とその話をしたばかりでしたが、まさか本人の公演があるとは。
(余談ですが、テレビジャパンというチャンネルでは、日本の番組を放送しています。
永住組のご家庭では、契約されているところもあります。)
公演では、これまでの研究が順を追って説明されていきました。
最近では、低酸素感知以外にも、血管新生促進の働きなどにも着目されており、
腎性貧血改善の薬だけなく、がんや目の疾患に対する治療の研究も進んでいるようです。
最後には、超低酸素環境のチベット族の、この領域の遺伝子変異の研究のお話まであり、内容は多岐に及びました。
発見はもちろんすごいことなんですが、その発見が世の中の役に立つようになるまでの、一つ一つの研究の積み重ねと、
そこに関わってきた多くの研究者の存在が印象的でした。











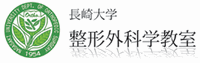
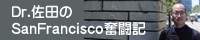

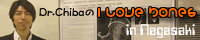







Comments