私は研究の世界においては、CTや骨微細構造の専門として認知されていますが、
前回話したように、臨床においてはDXAの重要性がとても高いので、DXAへのこだわりは強いです。
今日はDXA説明のコツを、治療モニタリングを中心にまとめてみます。
1)T-scoreでなくYAMで説明
世界標準はT-scoreで、YAMは日本のみ概念ですが、YAMの方が説明が容易です。
若者がYAM100%で、歳をとると誰でも90、80%と減りますが、
70%を下回ると骨粗鬆症と確定診断され、骨折しやすい状態と言えます。
2)治療効果は差でなく変化率で見る
治療効果は変化率で評価するのが世の決まりとなっています。
例えば50%が55%まで上がったとしたら5%アップでなく変化率としては10%アップです。
100%が105%まで上がったら5%アップなので、実は、骨密度は高くなると変化率は小さくなっていきます。
2)腰椎BMD
L1-4で評価します。半年で2~3%上がれば上出来です。
下がった時は、薬が効いてないと判定する前に、この半年間で起きたイベントを聞きます。
例えば何か病気をして入院を1ヵ月間してたとか、それだけでほとんどの方は骨密度の低下が生じます。
また、毎回+2%→+2%→+2%と直線的に上がるわけではなく、
+4%→+0%→+2% や、+4%→-2%→+4%みたいに、上がったり下がったりしながら、トータルとして上がることもあります。
1回下がったからといって、簡単に無効とは判定できません。
椎体骨折が発生するとその椎体のBMDは高くなります。変性側弯は多椎体のBMDを上げてしまいます。
いずれも、L1-4平均値の評価から除外しないといけません。
3)大腿骨BMD
大腿骨全体(Total Hip)と大腿骨頚部(Femoral Neck)で評価しますが、
前者の方が信頼性が高く、モニタリングは大腿骨全体(Total Hip)でします。
大腿骨BMDを上げる事は容易ではなく、半年で1~2%上がれば上出来です。
大腿骨は運動量に関係しますので、上がりが悪い方には、運動療法の指導もします。
大腿骨BMDは、実は左右差があり、ほとんどの施設では片方しか撮影しませんが、本来は左右とも測定ことが望ましいです。
4)そもそも早期発見治療が重要
YAM50%を70%にするには、40%の増加率が必要です。
しかしながら、ほとんどの薬は数年間で40%も増やすことができません。
治療薬は以前と比べて強力になったといえども所詮この程度で、本来はもっと強力な薬が必要です。
そのような薬のニーズはありますが、現在、新薬開発はほとんどなくなってしまいました。
よって今後も、早期発見、早期治療が重要と言うことになります。










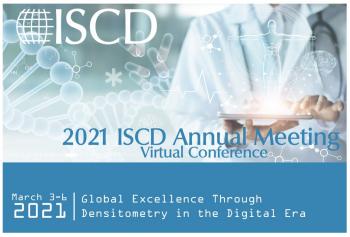

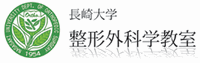
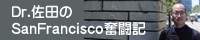








Comments