1年半ぶりの飛行機は、もう、感動でしたよ。乗り方(ルーチンの動き)、忘れてなかった。。
骨形態計測学会
今回、学会長がWeb開催をしないことを決定したため、かつ、私が、ランチョンセミナー、シンポジウム、座長x2、評議員会のお仕事があったため、現地参加を決めました。
とはいえハードルは未だに高く、私自身、もちろんワクチンは接種済みですが、
長崎大学の規定に則り、理由書を書いて、学長の承認をもらって(ドキドキ、、)、COCOA起動して、帰ってからPCRして(陰性)。
また、娘の幼稚園の規定により、土曜に帰ってましたが、日曜は家族に会えず、医局で過ごしました。
久々の現地での学会参加の感想は、、やっぱり現地はいいですね!
顔なじみのみんなに再会できて楽しかったですし、新しい知人も4-5人ほど増えました。
将来のコラボや講師依頼は、この輪の中から生まれます。
新しい情報も手に入りましたし、企業とのミーティングもできました。
倉林先生の女性医学の話、曽根先生のDXAの話、伊東先生の働き方の話、勉強になったな。
石川先生の活躍にも刺激を受けました(アカデミック破天荒、ある種の天然キャラであることが判明)。
同時期に、日整会総会がWeb開催されていたのですが、オンデマンド聴講の締め切りに気付いたのが終了3日前。
それまで1つもWeb聴講してないことに気づき、あわてて、5つの教育講演だけ聞きました。しかも単位目的で、ほぼ垂れ流しでした。
だって、職場には毎日仕事があるわけで、オンデマンド講演は、そりゃ後回しにされますよ。
一方、現地参加は会場に缶詰なので、もちろんしっかり聞くわけです。
この同時並行だったWeb開催と現地開催の差を強く実感した結果、やっぱり現地開催は大事だなと確信しました。













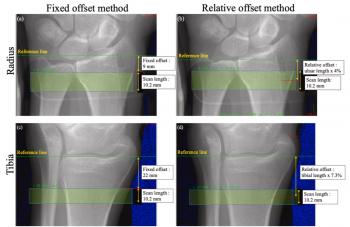
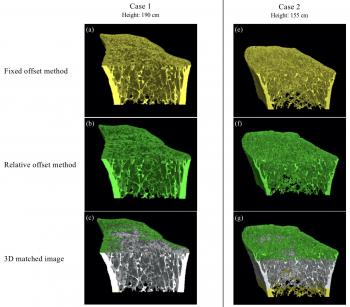


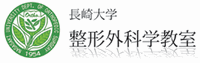
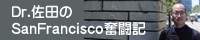








Comments